初級
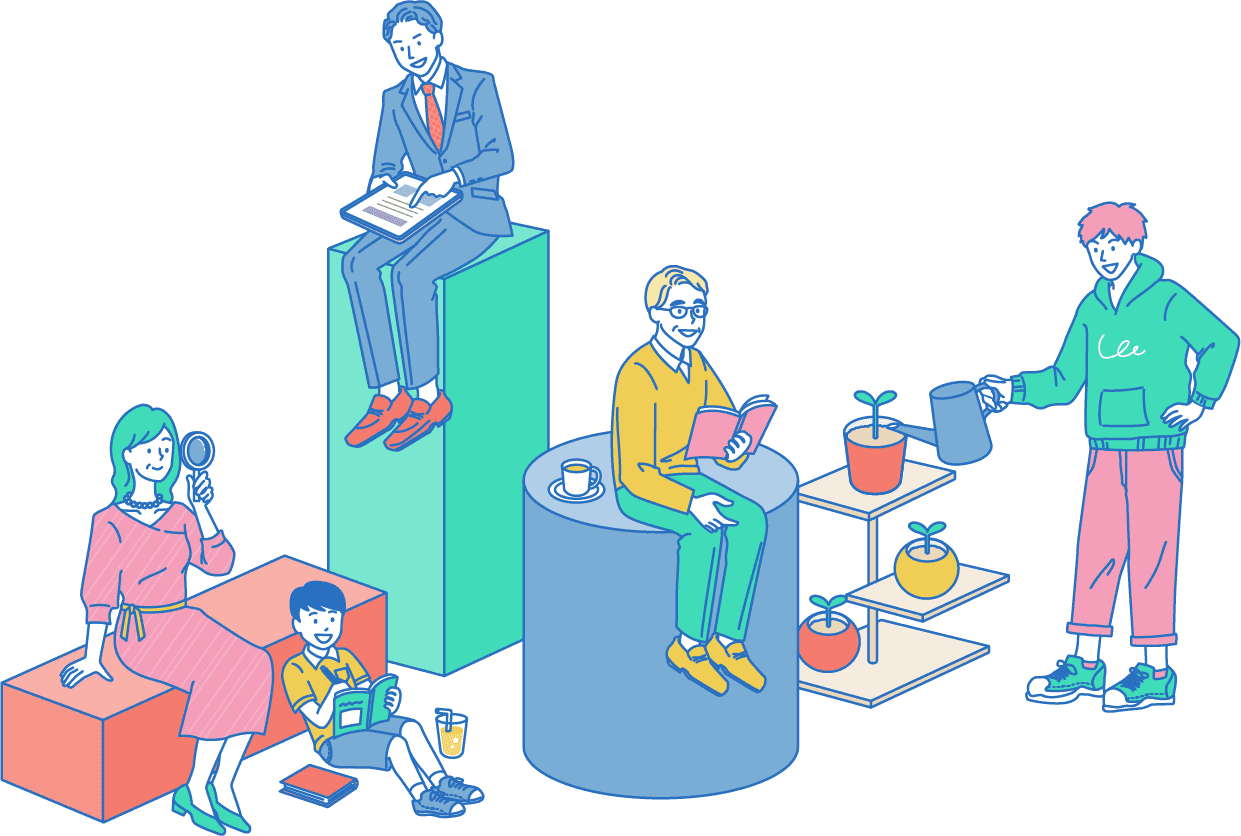
投資信託
制度を活用しよう!
NISAとiDeCo
どっちがいいの?
投資で税制優遇が受けられる制度として、NISAとiDeCoが挙げられます。これらの制度はよく比較されますが、税制優遇の内容や、投資可能商品など多くの違いがあります。この記事ではNISAとiDeCoの概要やメリット・デメリット、活用例について解説しています。NISAとiDeCoの違いがわからない、またこれから投資を始めてみたい方は、ぜひ最後までお読みください。
NISAとは?
NISAとは少額の投資であれば、運用益等に税金がかからないという制度です。一般的な投資では、運用益等が出るとそれに対して20.315%の税金がかかります。しかしNISA口座を使って非課税枠内で運用すると、運用益等に税金がかかりません。
旧NISA制度は3種類あった
2023年までの、NISAは3種類(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)あり、それぞれ非課税保有期間や年間非課税投資枠、投資可能商品などが異なり一般NISAは年間の投資元本120万円までであれば、5年間は利益が出ても税金がかかりませんでした。
2024年からは新しいNISAがはじまり、一般NISAが「成長投資枠」、つみたてNISAが「つみたて投資枠」となり、2つの投資枠が併用できるようになります。これまでのNISAは、一般NISAとつみたてNISAの併用はできませんでした。制度の恒久化や年間非課税投資枠の拡大などにより使い勝手の良い制度に生まれ変わりました。一方で、ジュニアNISAは2023年で廃止となりました。
〈2023年までのNISAの概要〉
| 一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
|---|---|---|---|
| 制度開始 | 2014年1月 | 2018年1月 | 2016年4月 |
| 非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 2023年末以降非課税期間が終了する ものは、18歳まで非課税で保有を継続可能 |
| 年間非課税投資枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
| 投資可能商品 | 上場株式・ETF・ 公募株式投信・REITなど |
長期・積立・分散投資に適した 一定の投資信託 |
上場株式・ETF・ 公募株式投信・REITなど |
| 払出制限 | なし | なし | あり |
| 年齢制限 | 18歳以上 | 18歳まで | |
〈 2024年以降の新しいNISAの概要 〉
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 口座開設期間 | 恒久化 | |
| 非課税保有期間 | 無期限化 | |
| 年間非課税投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有 限度額(総枠) |
1,800万円 (成長投資枠は1,200万円まで) |
|
| 併用の可否 | 可 | |
| 買付方法 | 積立投資のみ | 一括・積立投資 どちらも可 |
| 投資対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・ 投資信託等(制限あり)※ |
(金融庁開示資料等を基に作成)
※ ①整理・監理銘柄 ②信託期間が20年未満、毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
NISAのメリット
NISAはどのようなメリットがあるのでしょうか?主なものを2つ紹介します。
・投資による利益に税金がかからない
NISAは株式や投資信託の売却益、配当金・分配金など、投資で得た運用益に対して税金がかかりません。例えば100万円を運用して、10万円の運用益が出た場合、NISA口座を利用した場合は10万円がそのまま受け取れます。
仮に同じケースでNISA口座を利用しないで運用していた場合、手取りは約8万円弱となります。
・いつでも引き出しができる
NISAは、お金が必要になったタイミングで運用資金をいつでも引き出せます。
NISAのデメリット
一方、NISAにはデメリットもあります。利用する前にデメリットについても確認しておきましょう。
・元本割れする可能性がある
NISAの投資対象商品は、いずれも元本割れする可能性がある商品です。定期預金や国債のように、満期まで持っていれば、原則、元本割れしない商品の取扱いがありません。
・損益通算や繰越控除ができない
NISAは損益通算や損失の繰越控除ができません。
一般的な株式投資や投資信託で損失が生じている商品と、運用益が出ている商品がある場合、両者を相殺した利益に税金がかかります。例えばA商品で運用益が10万円、B商品で3万円の損失が出ている場合、A商品の運用益10万円に税金がかかるのではなく、B商品の3万円の損失と相殺した7万円に税金がかかります。
これを損益通算と言いますが、NISAで利益が出ても、NISA口座以外の投資商品と損益通算をすることができません。
また投資の損失は、確定申告をすれば翌年から3年間損失を繰り越すことができます。仮に令和元年で30万円の損失が出て、令和2年に10万円、令和3年に10万円、令和4年に12万円の運用益が出た場合、令和4年度は2万円に対して税金がかかります。
しかしNISA口座で運用した場合、損失の繰越控除が利用できません。
【繰越控除のイメージ】
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益 | ▲30万円 | +10万円 | +10万円 | 12万円 |
| 前年からの繰越損失 | なし | ▲30万円 | ▲20万円 | ▲10万円 |
| 税金がかかる金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 2万円 |
iDeCoとは?
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称です。老後の資産形成を後押しするための制度で、掛金を支払い、あらかじめ用意された中から自身で商品を選んで運用します。
iDeCoのメリット
iDeCoは老後の資産形成を後押しするために、3つの税制メリットがあります。各メリットについて詳しく紹介します。
・掛金が全額所得控除される
iDeCoの掛金は全額所得控除されるため、税金が軽減されます。
例えば、所得300万円の場合、この300万円に税率(所得税と住民税合計)15%をかけた金額が支払う税額となります。しかしiDeCoに加入して、年間掛金20万円を支払うと、所得から20万円分控除できることから、所得を300万円から280万円に減らせます。
税金を計算するときの基礎になる所得金額が減るため、15%をかけた税額も減少できることがおわかりいただけるでしょう。
・運用益に税金がかからない
iDeCoもNISAと同様、運用益に税金がかかりません。iDeCoの運用益は再投資されます。
・受取時も税制優遇がある
iDeCoで運用した資産は、原則60歳以降に受け取れます。受け取り方法は一時金として受け取る方法、年金として受け取る方法、一時金と年金の組み合わせのいずれかから選べます。
一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除が受けられるなど、どちらの方法で受け取っても税制優遇が用意されています。
iDeCoのデメリット
iDeCoにもデメリットはあります。主なデメリットを2つ紹介します。
・元本割れする商品もある
iDeCoの商品ラインナップは金融機関によって異なりますが、投資信託が多く、元本割れする可能性があります。ただしiDeCoの商品ラインナップには、満期まで持っていれば元本割れしない定期預金などの元本確保型の商品も用意されています。
・原則60歳まで受け取れない
iDeCoで運用している掛金は、原則60歳まで引き出しができません。そのため運用期間中に急にお金が必要になっても、NISAのように口座から引き出せるわけではない点に注意が必要です。
iDeCoとNISAの違い
iDeCoとNISAの違いをまとめると、以下のとおりになります。主な違いとしては、NISAはいつでも引き出しができますが、iDeCoは原則60歳まで引き出しができないこと、税制優遇についてはiDeCoの方が多いことが挙げられます。
| NISA (成長投資枠) |
NISA (つみたて投資枠) |
iDeCo | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上 | 20歳以上60歳未満※1 | ||
| 非課税期間 | 無期限 併用可能 |
運用期間中 | ||
| 購入方法 | 一括購入・積立 | 積立 | 積立 | |
| 運用商品 | 投資信託・上場株式など※2 (一部対象除外あり※3) |
長期の積立・分散投資に適した一定の条件を満たす投資信託など※4 | 運用管理機関が指定する投資信託・定期預金など | |
| 金融機関変更 | 各年ごとに変更可能 | 変更可 | ||
| お金の引出し | いつでも可能 | 原則60歳まで不可 | ||
| 投資上限額 | 年間 | 240万円 併用可能 |
120万円 併用可能 |
加入者によって上限が異なる※5 |
| 累積 | 1,800万円 (簿価残高方式で管理枠の再利用が可能) |
- | ||
| 1,200万円まで | ||||
| 口座管理手数料 | なし | 加入者負担あり | ||
| 運用商品の 購入時手数料 |
ファンドによりかかるものとかからないものがあります | なし | なし | |
| 税制優遇等 | 拠出時 | なし | 全額所得控除 | |
| 運用時 | 譲渡益および分配金等の運用益非課税(損益通算不可) | 運用益非課税 | ||
| 受取時 | なし | 一時金:退職所得控除 年金:公的年金等控除 |
||
※1 20歳に満たない場合でも、厚生年金被保険者であれば加入対象となります。(一定の要件のもと65歳未満まで加入可能)
※2 南都銀行では投資信託のみが対象となります。
※3 ①整理・監理銘柄②信託期間が20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
※4 南都銀行では一定の条件を満たす投資信託のみが対象となります。
※5 加入者により、加入条件(加入可否・金額など)が異なります。
iDeCoとNISAの使い分け
iDeCoとNISAはどのように使い分ければ良いのでしょうか?活用方法の一例を紹介します。
・中期的な目標のために投資をするときはNISA
NISAは、非課税保有期間が無期限で払出し制限がないため、子どもの教育費準備や住宅ローンの繰り上げ返済資金など、20年以内の中期的な目標に向けて投資をするときはNISAが向いています。
・老後の資産形成を目的とする投資ならiDeCo
iDeCoは3つの税制優遇を受けられます。また原則60歳まで引き出しができないため、運用の目的が老後に向けた資産形成と決まっているときは、将来の自分への贈りものとしてiDeCoを活用すると良いでしょう。
まとめ
投資で税制優遇が用意されている制度としては、NISAとiDeCoがあります。NISAとiDeCoは、非課税保有期間や年間非課税枠、投資可能商品、税制優遇の内容などの違いがあるため、制度の違いやそれぞれのメリット・デメリットを理解して、投資の目的に応じて上手に使い分けることが大切です。
どのような投資をすればわからないという方は、まずは南都銀行に相談してみましょう。
ご相談は南都銀行へ!!
窓口で相談!
電話で相談!
〈ナント〉ダイレクトセンター
0120-710-654
受付時間/平日9:00~17:00 土日10:00~17:00
投資信託のご注意事項少額投資非課税制度(NISA)に関するご注意事項
- 本サイトの記事は一般的な情報提供を目的に作成しており、商品を推奨・勧誘するものではありません。
- この記事の情報は当行が信頼できると判断した情報源から作成したものですが、その内容の正確性、確実性を保証するものではございません。
- 記事の内容は、予告なく変更することがございます。
